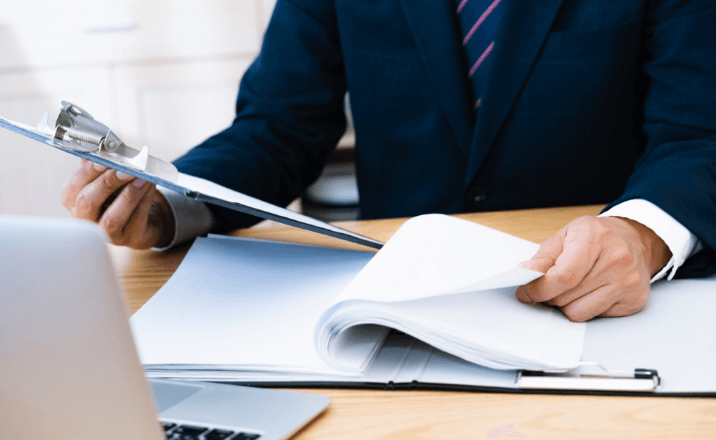2020.03.13
- デジタル・フォレンジックス
4.DFが重要となってきた背景

こんにちは、LXの深山です。
今回は、前回に引き続き「デジタル・フォレンジックス(DF)」の紹介ですが、昨今なぜ重要視されるようになってきたのかについて解説してみたいと思います。
まず、私が「金融庁 証券取引等監視委員会 特別調査課」に所属していた時期に聞いたのですが、ライブドア事件の捜査に絡んだ「堀江メール問題」(2006年2月〜)が端緒となったそうです。
事件の詳細はリンク先をご覧戴きたいのですが、この一連の事件は証券取引法(現在の金融商品取引法)に関連した経済事件であり、ライブドア事件自体は特捜部が自ら捜査を行ったものでしたが、当時の監視委員会の調査官は押収してきたパソコンや電子機器をそのまま起動して閲覧・調査していたため、電子データの証拠には不意の証拠改竄のリスクが付き纏うことを意識したそうです。そこで、当時の特別調査課課長が米国のSECではどの様に対処しているのかということを調べ、特別プロジェクトチームを立ち上げたのが経緯となりました。
私はたまたまそのタイミングで任期付き職員として当該プロジェクトチームに所属させて頂き、予算のないところから予算獲得、チーム増強、研修受講、設備や機材の整備を踏まえて実践的に調査現場で利用して行ったのでした。
その時期にさらにご縁があり、関東管区警察学校の「情報技術解析専科」に入校させていただき、学ぶ機会があったのですが、当時から既に高度なデジタル・フォレンジックスの機能を保有していた警察機構(警察庁、警視庁、各都道府県警察)にも、単なる鑑識とは別にITに関する高度な能力を保持しなければ捜査に支障を来すという契機があったという話を聞きました。それが、「オウム真理教事件」の最終局面で信者が遠隔操作で都内にあったアジト(拠点)のパソコンを遠隔消去してしまったという事があったそうです。
その後、ネットワークに関する技術、電子データの復元に関する技術、保全技術、解析技術などが高められていくことになりました。その際、かつては新卒一括採用が一般的だった警察機構で、IT企業に勤めているエンジニアなどを中途で採用するということも積極的に行われ、技術力・組織力が高められていきました。その結果、その後の捜査では情報技術解析専科を経た専門官や通常の捜査官にも使えるツールが広く普及し、捜査力の向上が図られたとの事です。(参考)
このような経緯で、経済事件に関して監視委員会がDFを活用する事が当たり前になり、民間でも経営や経済活動において書面資料より電子機器によるデータが圧倒的に多くなってきた事で、不正調査や不祥事対応でも電子データの保全・解析・分析が重要となってきたと言えます。
本記事の監修者
 顧問 公認不正検査士 経営修士(MBA)・DCM修士 / Office Miyama代表
深山 治OSAMU MIYAMA
顧問 公認不正検査士 経営修士(MBA)・DCM修士 / Office Miyama代表
深山 治OSAMU MIYAMA
- 専門分野
- 会計・財務アドバイザリー, デジタル・フォレンジックス
デジタル・フォレンジックスの事例
リスクマネジメントに関連するサービス
よく読まれている記事
サービスカテゴリー
- デジタル・フォレンジックス

こんにちは、LXの深山です。
今回は、前回に引き続き「デジタル・フォレンジックス(DF)」の紹介ですが、昨今なぜ重要視されるようになってきたのかについて解説してみたいと思います。
まず、私が「金融庁 証券取引等監視委員会 特別調査課」に所属していた時期に聞いたのですが、ライブドア事件の捜査に絡んだ「堀江メール問題」(2006年2月〜)が端緒となったそうです。
事件の詳細はリンク先をご覧戴きたいのですが、この一連の事件は証券取引法(現在の金融商品取引法)に関連した経済事件であり、ライブドア事件自体は特捜部が自ら捜査を行ったものでしたが、当時の監視委員会の調査官は押収してきたパソコンや電子機器をそのまま起動して閲覧・調査していたため、電子データの証拠には不意の証拠改竄のリスクが付き纏うことを意識したそうです。そこで、当時の特別調査課課長が米国のSECではどの様に対処しているのかということを調べ、特別プロジェクトチームを立ち上げたのが経緯となりました。
私はたまたまそのタイミングで任期付き職員として当該プロジェクトチームに所属させて頂き、予算のないところから予算獲得、チーム増強、研修受講、設備や機材の整備を踏まえて実践的に調査現場で利用して行ったのでした。
その時期にさらにご縁があり、関東管区警察学校の「情報技術解析専科」に入校させていただき、学ぶ機会があったのですが、当時から既に高度なデジタル・フォレンジックスの機能を保有していた警察機構(警察庁、警視庁、各都道府県警察)にも、単なる鑑識とは別にITに関する高度な能力を保持しなければ捜査に支障を来すという契機があったという話を聞きました。それが、「オウム真理教事件」の最終局面で信者が遠隔操作で都内にあったアジト(拠点)のパソコンを遠隔消去してしまったという事があったそうです。
その後、ネットワークに関する技術、電子データの復元に関する技術、保全技術、解析技術などが高められていくことになりました。その際、かつては新卒一括採用が一般的だった警察機構で、IT企業に勤めているエンジニアなどを中途で採用するということも積極的に行われ、技術力・組織力が高められていきました。その結果、その後の捜査では情報技術解析専科を経た専門官や通常の捜査官にも使えるツールが広く普及し、捜査力の向上が図られたとの事です。(参考)
このような経緯で、経済事件に関して監視委員会がDFを活用する事が当たり前になり、民間でも経営や経済活動において書面資料より電子機器によるデータが圧倒的に多くなってきた事で、不正調査や不祥事対応でも電子データの保全・解析・分析が重要となってきたと言えます。
本記事の監修者
 顧問 公認不正検査士 経営修士(MBA)・DCM修士 / Office Miyama代表
深山 治OSAMU MIYAMA
顧問 公認不正検査士 経営修士(MBA)・DCM修士 / Office Miyama代表
深山 治OSAMU MIYAMA
- 専門分野
- 会計・財務アドバイザリー, デジタル・フォレンジックス

- 専門分野
- 会計・財務アドバイザリー, デジタル・フォレンジックス